竹下内閣時の1988年12月24日に消費税法(税率3%)が成立し、1984年04月01日から適用されました。
日本で初めての「消費税」導入です。
当時事務系プログラマーをしていた私たちは適用日に向けてプログラムの修正作業をしました。
その消費税関連のプログラム修正で、半年後に3000万円が消えました。

テスト結果、これで良いですか?
お金が動くプログラムのほとんどに関連する修正ですから、名古屋事業部所属のプログラマ3名は、施行のかなり前から、かかりきりで関連システムを特定して修正箇所をピックアップし法案成立にそなえていました。
- 当時、windowdは存在していません。
- メインフレームコンピュータIBM system34は大型冷蔵庫3個分くらいの大きさでした。
- RPG(レポート・プログラム・ジェネレータ)言語で書かれたプログラムをテスト環境にコピーして修正してテストデータで走らせて、結果を経理担当者が「そろばん」で検算していました。
プログラマごとに割り振られたシステムの該当プログラムの必要箇所をちまちま修正して単体でテストしていきます。
最初は大変ですが慣れれば修正はパターンですから早くなっていきます。
単体の結果が良ければそのシステム全体でテスト評価してOKならば次のシステムの修正に移行します。
全てのシステムのテスト検算の結果、経理から無事OKが出ました。
04月01日の施行日の前日深夜にシステムを止めて、関連プログラムをすべて新しいものと置き換えて朝の本番を迎えました。
どんなにテストしても本番の稼働では何本かの修正が発生しますから、それを大急ぎで修正してエラーを潰していきます。
数日でほぼ正常運転になりました。やれやれお疲れさまでした。
何かが変わるとき(昭和が突然終わった時など)のプログラマはいつもこんな感じです。
それは半年後に発覚しました
半年ほど経過したある日、課長から私にある事実が告げられました。
「工場間請求システムの金額が合わない。消費税の端数計算、どうなってる?」
私は間違って入社した一流企業は会社規模が大きいのです。
各事業部に工場が数か所ずつあります。空いている工場施設で他の事業部で受注した仕事の生産を行います。
他の事業部に仕事を発注した形になりますから、それぞれの仕事を相殺しながら請求書を発行します。
その金額が合わなくなったと経理から言われたのです。
- 調べたら、このプログラムだけ端数の処理が「切り捨て」になっていました。
- 消費税を計算するとき端数の処理は「四捨五入」しますが、間違って切り捨てた一件当たりの金額は1円単位です。
- それが半年の大量の取引で約3000万円の不足が発生したのです。
「ああっ、やってしまった。」と、それしか考えられませんでした。頭が真っ白でした。
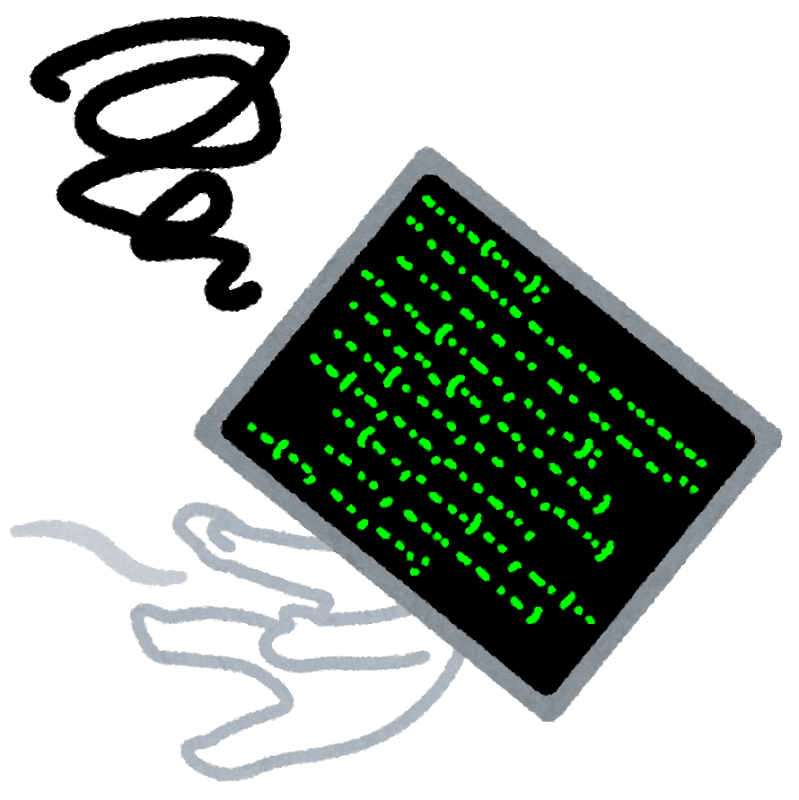
首にはなりませんでしたが、ふるえます
テストではわからなかった「四捨五入」「切り捨て」の間違いが発覚するのに半年かかりました。
いやいや たった半年で発覚しました。
たまたま「工場間請求」という社内の取引部分のミスだったので、経理同士のお話し合いで金額の訂正が行われましたから、直属の上司(課長)からの𠮟責で穏便にすませていただきました。
これが得意先や関連会社への請求だったらお金が戻ってこないことも考えられました。
いまだに、あの時の恐ろしい感覚を思い出してふるえます。
おあとがよろしいようで
企業のシステム障害のニュースを見るたびに、なんとも言い難い気持ちになります。
私は運が良いのでしょうね。
数年後、私はプログラマをやめましたが、いまでも生き延びていますから。
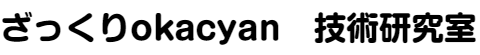
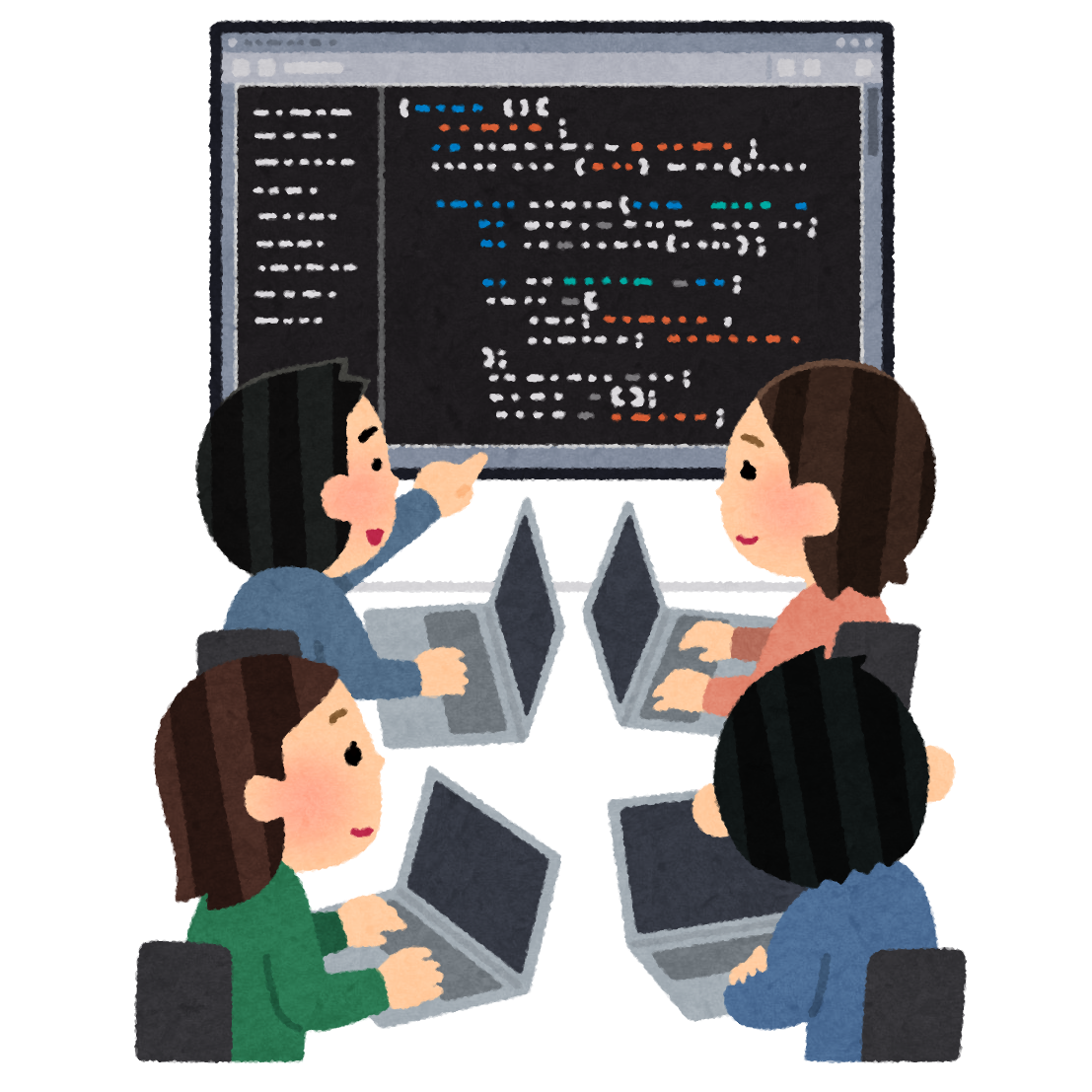


コメント